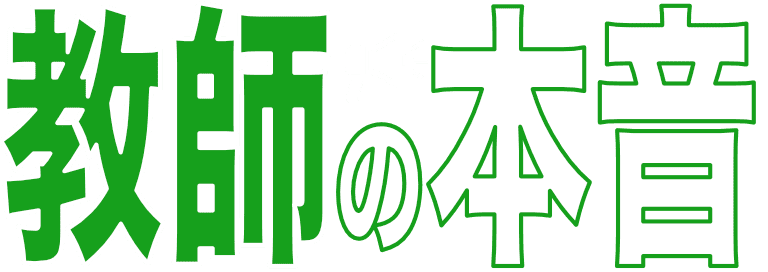ご存知の方も多いかもしれませんが、2013年の滋賀県大津市で起きたいじめ自殺事件。
この事象をきっかけに施行された、いじめ防止対策推進法。
この法律の影響で、それまでのいじめに対する教師の対応も大きく変わることになりました。
しかし何事もそうですが、制度や条件をつくるとハックする人が出てくるように、この法律の影響によって現場の教師や保護者・生徒たちは


など、いわゆるグレーゾーンのいじめ(例:いじり、冗談など)も増え、そこに対する対応で煩雑になってきたのは事実です。
そこでこの記事では、学校の現場で起こりがちなトラブルについて
- いじめなのか、そうじゃないのか。
- 最適な指導や対応は、なんなのか?
- この法律に問題点はないのか?
これらについて、一緒に考えてみたいと思います。
目次
そもそも、いじめ防止対策推進法とは?
冒頭で紹介した通り、2013年に施行されたいじめ防止対策推進法。
いじめに関して
- 被害者がいじめられている事実を知りながら、学校や教師が放置していた
- 加害者に対して指導が不十分で、いじめが継続していた
- 学校側が保護者に対して、きちんとした説明責任を果たしていなかった
など、さまざまな不適切な対応が滋賀県大津市で起きた事件をきっかけに大きな問題となり、同法律が制定され施行されました。
ネット番組でも議論されている内容です。
このいじめ防止対策推進法が学校の現場にもたらした影響のうち、もっとも難しいのはグレーゾーン時の対応と考えています。
いじめの定義とは?

文部科学省が発行している児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導状の諸課題に関する調査によると、いじめの認知件数は昔に比べて大幅に増加しています。

昔と比べて大幅に増加した「いじめ」の認知件数
(これは前向きな意見ですが)10年前では把握すらされなかったいじめ(いじりや嫌がらせなど)も、件数として認知できるようになりました。
いじめの発見のきっかけは,
・「アンケート調査など学校の取組により発見」が55.4%(前年度54.2%)と最も多い
・「本人からの訴え」は17.6%(前年度17.6%)
・「当該児童生徒(本人)の保護者からの訴え」は10.1%(前年度10.2%)
・「学級担任が発見」は9.6%(前年度10.4%)
報復を恐れたり、いわゆるチクったと思われたくないから、相談すらできなかった。
そのようないじめが、法律ができて(アンケートなどによって)明るみになったことは、大きな恩恵の一つです。
またこの法律により、学校や教師が認知した「いじめ」については必ず
- 事象の確認(聞き取りなど)
- 対応、報告(継続指導や見守りも含む)
を行う必要があります。
その甲斐もあってか、50万件を超えるいじめの8割近くは解決しているもの(解決済み)となっています。

いじめの定義は?
いじめ防止対策推進法では、いじめの定義を
この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じるものをいう。
引用 いじめ防止対策推進法
と定義しています。
一昔前であれば継続性も重要なポイントとして考えられていましたが、一度きりの行為だとしても「いじめ」として認定されるということになります。
そしてその行為は暴力行為に留まらず、心理的に苦痛を感じれば「いじめ」になるということです。
学校現場のトラブルはすべて「いじめ」になる?

法律によるいじめの定義は先ほど紹介しましたが、それも含めて「いじめ」の位置付けとして
- 刑法(犯罪)に該当するもの
- 民事上の損害賠償責任が成立するもの
- いじめ防止対策推進法によるもの
この3つが存在します。
刑法に該当するものであれば
- 暴行罪
- 傷害罪
- 脅迫罪
- 強要罪
- 名誉毀損罪
など、(正確には14歳未満は”虞犯”として扱われ、犯罪としては成立しない)罪として罰せられます。
一方、民事上の損害賠償責任が成立するいじめについても
- いじめの被害者に、なんらかの損害が発生した。
- 社会通念上許される限度を超えて、客観的にも違法とされる行為
- 又は、明らかに相手の心身に苦痛を与える意図と態様を持って行われた行為
これらについては、損害賠償責任が成立するいじめであると判断されています。
難しいのは、学校で判断するもの。
すなわち、3の「いじめ防止対策推進法によるもの」です。
主観的な物差しで決まるいじめは、認定される範囲が広くなってしまう
いじめ防止対策推進法でいう「いじめ」とは、繰り返しになりますが
この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じるものをいう。
引用 いじめ防止対策推進法
というものであり、刑法や民事上の損害賠償責任が成立するいじめと比べると、いじめとして認定される範囲が広いです。
例えば
- 無視される
- はみご(ハバにされる)
- LINEグループから外される
などは刑法や民法の観点から見ると不利益を被ったとは言えない内容ですが、「辛い思いをした」という心理的ないじめとして認定されます。
この法律の難しいところは、いじめの被害者が心身の苦痛を感じているかどうかという「主観的な」内容が、いじめ認定の判断要素になっている点です。
これは「いじめ」でしょうか?

具体的なケースを見ていきます。
例えば
- AさんはBさんから「傷つけられるような言葉」を言われた。
- AさんはBさんの発言でショックを受け、それをきっかけにAさんは学校に行けなくなった。
- Bさんに事情を確認したところ、「Aさんが言ってきたから、言い返した」とわかった。
このような場合。
ショックを強く受けてしまった(言い返せなかった、学校に行けなくなってしまったと主張する)Aさんが被害者になる可能性が高いと考えられます。
もちろん、解決に向けてAさん・Bさんと一緒に(同席か別々かはわかりませんが)話し合いをすると思います。
しかし、ともに「言った・言わない」の証拠がなければ、被害の状況を鑑みて「Bさん」が加害者となってしまう可能性が高いです。
Aさんが本当に(最初に)言ったのか、学校側はわかりません。
なにせ、学校よりも家庭やプライベートで過ごす時間の方が長い訳ですし。(在校6時間に対して、プライベートは18時間)
本当はBさんが最初だったかもしれませんが、学校に来れなくなったAさんが「最初にBさんから言われた」と(主観的に)発言すれば、Aさんは学校に来れなくなるほど精神的な苦痛を受けているので被害者として扱われる可能性が高いです。
真の意味での「被害者」と「加害者」を判断するのは難しいですが、学校の現場ではそれを明らかにできるほどの時間的余裕もなければ、法律の専門家でもありません。
現状の対応で言えば
- Aさんが学校に来れるよう、働きかける
- Bさんに対して、Aさんに謝罪するよう指導する
(AさんがBさんに対して謝罪するかどうかは不明)
と、動くのが一般的です。
真相は確かめられることなく、より大きな被害を被った生徒(この場合だと学校に来れなくなるほど苦痛を受けたAさん)のフォローをしていくことになります。

いじめをなくすために必要なことは何なんでしょうか?
被害者を支援し、加害者に指導を行う。
これは義務であり、法律があろうとなかろうと児童・生徒の教育に関しては大事なことです。
一方で、法律があるからこそ悪用したり、法律があるからこそ現場が振り回されたりしていることも事実です。
2013年に施行された「いじめ防止対策推進法」は、総論賛成各論反対のような印象です。
それを現場のみで判断せざるを得ない状況も、非常に限界があります。
参考
#教師のバトン から見る教師の限界と、個人レベルで対策してきた解決方法
いじめ撲滅に向けて、学校や教師がすべきことは何なのでしょうか。
あわせて読みたい記事