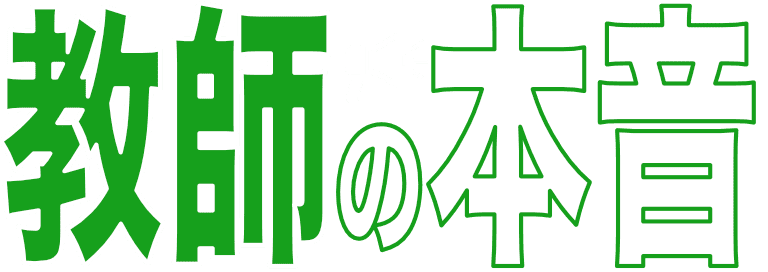教師に限ったことじゃないですが、教えるということは、ただ知識や技術を伝えるだけでは上手くいかないです。
なぜか?
「信頼感」が必要不可欠だからです。
年代別の指導方法で話しましたが、年代ごとに求められている「スタンス」「適した指導方法」というものは存在しています。
年齢やキャリアというファクターが、信頼感に作用することも当然あります。(否が応でも)
「年齢(キャリア)」によって、信頼感が増していく
これは、まぎれもない事実です。
しかし
- 若くたって、多くの信頼を集めている教師はたくさんいますし
- 反対に、年だけ重ねたぺらっぺらの教師もたくさんいる。
これもまた、まぎれもない事実です。
違いはなにか?
教える立場として「必要なことはなにか?」をしっかりと把握出来ているか、そうじゃないか。
普通は、キャリアを積んで自然と身についてくる「教師の役割」について、若いうちから(または普段から)把握できているか。
これらができているか、どうかだと思います。
もう少し、わかりやすく言うと
教師は何者であるべきか?
これをしっかりと把握していると、信頼感を得やすい、ということです。
昔からよく「教師には五者の役割が必要だ」と言われています。
本日はその5者(+1)について紹介していこうと思います。
信用を得やすくなるような声のかけ方について知りたい人はコチラ
目次
教師とは、学者である

100を知ってこそ、1を教えられる。
わかりやすさとは、「教える側に、膨大な知識があること」によって、初めて生まれるものです。
さらには、自分が「勉強をする姿」を見せることによって、生徒や同僚に波及させる効果も期待できるでしょうね。
以前いた学校では、私自身の学力や知識量が追い付かず、授業の無い空きコマのときは、休み時間もなく、ひたすら勉強していました。
その姿をみた同僚(私より少し上)の一人は

○○先生(私)は、いつも勉強しているね。すごいよ。
といっていました。
本当は、そうしないと授業が成立しなかったから。
なかば必然的に、勉強をしなくてはいけなかったというだけです。
しかし、その同僚曰く

いい刺激になる。
と言っていました。
ポジティブな人、ひたむきな人の周りには、同じ人達が集まります。
そういった意味でも、常に勉強する姿勢というのは、大事になってきます。
教師とは、役者である

教師はどうしても「人前に立つ」ことが必要です。
人前に立って、人を惹きつけること
これすなわち、役者と同じです。
見た目でアドバンテージを得る人もいるでしょうが、幸い芸能人と違って、教師でいう役者は中身を重視されやすいです。
さっき話した知識量もそうですが、役者になるためには、テクニックも必要です。
話す時の抑揚(緩急)、間の取り方、視線の配り方、服装髪型…。
コミュニケーションをとるうえで、有効な手段やテクニックはたくさんあります。
生徒のモチベーションをあげる指導、ポイントはこの6つ!で話した6つのテクニックなんかも、非常に有効です。
参考
人が何かをする際のきっかけや、目的意識のこと。モチベーション。 教える側も教えてもらう側も、モチベーションひとつでその吸収が随分と変わってきます。教師が生徒の上に立ち[…]
これは、「プライベート」と「仕事」を分ける意味でも、非常に大きな意味をもちます。
おかげで友人に見られた際、全然違うと笑われたこともあります。
教師とは、易者である

易者とは本来、占いによって、相談者の人生におけるアドバイスをする人のことです。
ここで言いたいのは、生徒の不安をきっぱりと切り捨ててあげられる人のこと。
または、生徒の不安を取り除いてあげられる人のこと。
この意味で、易者という表現を使っています。
ウソはよくありませんが、たとえば

合格率5割か…不安だな
と不安がっているような生徒が、あなたのところへ相談に来たとします。
そんなとき

大丈夫、君は絶対にうまくいく
と、背中を押してあげるようなサポートをするべき、ということです。
悩む時間は、もったいないですからね。
教師は、芸者である


歌って、踊れってか?
そうじゃ、ありません。
場を楽しくしてあげること、という意味です。
「役者」と近いところがありますが、役者は先生が、芸者は生徒が主役です。
授業の中で、「笑い」や「わくわく感」があると、五感に訴えかけることができます。
過去記事「脳科学にそった効果的な教科指導、5つのポイント」で話していますが、五感を使うことで海馬が刺激され、記憶に残りやすくなります。
あなたも経験あるんじゃないですか?
先生の授業を振り返ってみて、その先生の話の中で、覚えている(印象に残っている)のは
無駄話、雑談も含めて「楽しかった」話題
だ、ってこと。
教師は、医者である

相手の性格に応じて、それぞれにあった処方箋、アドバイスを示すこと。
こればかりは、キャリアが大いに関係してきます。
自身が歩んできた経験も、モノをいいます。
適当にわかったつもりで答えるのが、一番の信頼を失う行為になるからです。
生兵法といってもいいかもしれませんね。
生徒の質問を聞きながら
- 理屈を追及するのか、考えるのが苦手なのか
- 楽観的か、悲観的か
このような相手の特性を考えて、的確なアドバイスをしてあげなくてはなりません。
逆に、これができれば、一気に信頼を勝ち取ることができます。
教師は、保護者である

同じく、キャリアが必要なことで、医者に代わるもの(または同等な位置づけ)としては保護者という視点も、大事になってきます。
親になった今ならよくわかります。
子どもの育て方は「本当に、これでよいのか?」という不安が、常に付きまといます。
親目線に立ってあげることで、親の理解(または協力)が得られる。
親の理解が得られることで、生徒は納得する。
理解の上に、納得は存在しています。
参考
効果的な教育的指導には、愛・保護者の理解・生徒の納得が必要?
福井県池田町の町立池田中学校で今年3月14日、2年生の男子生徒(当時14歳)が校舎から転落して死亡する問題が発生し「男子生徒は担任と副担任から繰り返し厳しい叱責を受け、精神的に追い詰められて自殺に至った」[…]
ネグレクトのように、親が生徒の成長に対して「無関心」なことも多くなってきています。
教育の現場では、たびたび直面しますよね?
そういう場合には、あなたが、(物理的な意味ではなく)保護者になり生徒のよき理解者でいてあげる、ということも重要になってきます。
医者のように、本質を見抜いて的確迅速に処方することが難しいようなら、保護者という視点からアプローチをかけてみるのも、一つの手です。
まとめ
上手く教える、というのはただ単に「知識や技術を伝える」だけではダメです。
信頼があってはじめて成立し、その信頼感が増すことによって、「上手く教える」ことができるようになります。
- 学者
- 役者
- 易者
- 芸者
- 医者(保護者)
ぜひ、「思うようにいかない」と悩んでいる人は、この五者(または六者)を意識してみてください。
あわせて読みたい記事