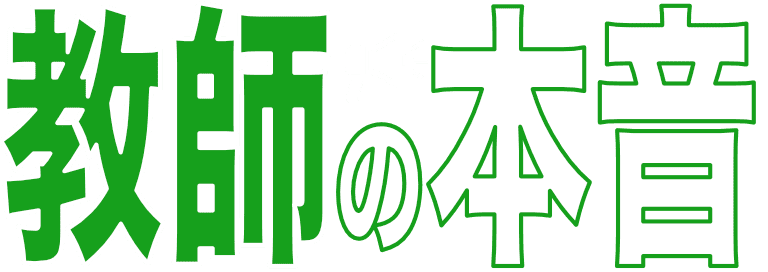人が何かをする際のきっかけや、目的意識のこと。
モチベーション。
教える側も教えてもらう側も、モチベーションひとつでその吸収が随分と変わってきます。
教師が生徒の上に立ち
- 威圧的
- 高圧的
に指導する時代は、過去のモノです。
参考これからの教師の仕事はどう変わる?!働き方やスタイルの変化を予想してみる
こちらが何もしなくても

この人についていく

この人に認められたい
このように意識して、ついてくる生徒に対しては特に、こちらがあれこれ施策を講じなくても問題はありません。
問題は、ついてきそうでついてこない子。
または、「全くついてこない」子です。
後ろ向きな生徒に対して、まずは
- モチベーションをあげること
- そして維持させてやること
これが非常に重要になってきます。
そのために必要なテクニックは以下の6つです。
目次
「楽しく学べる」環境をつくって生徒のモチベーションを上げる

割れ窓理論をご存知ですか?
そのまま「Broken Windows Theory(ブロークンウィンドウ理論)」なんて言ったりもします。
これは
- 割れた窓を放置すると、誰も関心を寄せていない、というサインになる。
- やがて軽微な犯罪が増える。
- 環境の悪化。
- 凶悪犯罪が増える
という流れをとると考える理論。
ポイントは
- 治安悪化のルートを止めるべく、些細なほころびから、徹底的に排除する。
- すると、治安が回復していく
です。
有名なところでいえば
- ニューヨーク市
- ディズニーランド・ディズニーシー
- Apple(スティーブジョブス)
などがあげられますでしょうか。
彼は、80年代、自身の失敗などによりApple社を追放されます。
その後10年かけて、Appleの業績が落ち込みつづけAppleはもはや沈む寸前。
そんな90年代後半に、ジョブスは再び代表に就きます。
彼がまず行ったことは、環境を整えることでした。
ペットの持ち込み禁止や、汚い作業環境の改善など、社内の意識改革を徹底的におこない、モチベーションのアップをはかっていきました。
その後のApple社の業績回復は、ご存じのとおりです。
学校教育においていえば、挨拶ができない、ごみが散らかっている、など。
ついつい見逃してしまいそうな変化にこそ注意を払い、環境を整えること。
これが重要です。
モチベーションを上げるための最低条件だと、思っていてください。
まずは期待させて、生徒のモチベーションを高めてあげる

次に「出来ない」「無理だ」などの否定的・悲観的な言葉を繰り返させないことです。
大人でも
- 高い障壁
- 逆境
を打ち破って前に進むことは、容易ではありません。
歩みを止めるのは、絶望があるからではありません。あきらめてしまうからです。
その反対に、歩みを進めるのは希望があるからじゃありません。意思があるからです。
私が好きなマンガの一つ「ARMS」に出てくる一説です。
そこに希望があり(または探そうとし)、意思をもって進むようになる。
まず、教師がすべきことは
生徒に希望を持たせ、期待させること。
これが、モチベーションを維持させるうえで、非常に大事です。
相手の成功を前提に会話することで、モチベーションがアップする

生徒から

先生、私って本当に大丈夫なの?
と相談されたとき、教える立場である教師は「迷い」を見せてはいけません。
疑うことなく「成功を前提に」話をすすめます。
この話の進め方については年代によって工夫が必要でしょうから、詳しくは生徒との対応、年代別の指導方法をご覧ください。
否定、愚痴、揚げ足取り、嫌味…。
その言葉を聞かされて「モチベーションが上がる」「維持させる」ことは、絶対的に不可能です。
生徒が迷っていたり、不安があるようなら
教師として「迷わず」「成功を前提に」話をすすめてあげる。
こうすることで、生徒はモチベーションを維持しやすくなります。
「短期目標」を繰り返し話すことで、モチベーションの維持をはかる

人はみな、器用そうで不器用です。
いきなりでかい山を越えられませんから、初めは小さな目標を立てそれをこなしていくことが大事です。
「成果をあげるためには、たった2割を集中すればよい?」でも話していますが、成功する秘訣の一つとして
やるべきことをチャンクダウンし、小さな一歩から着手する
というものがあります。
参考
チャンクダウンとは、細分化させるということ、または短期目標と言い換えることができます。
細分化された短期目標が具体的であればあるほど、インパクトがあります。
何度も繰り返し言うことでその目標を強く意識でき、モチベーションが上がります。
- この1問を解いてみよう。
- 15分だけ集中してみよう。
どんなことでも構いません。
短期目標を明確に定めてあげて、繰り返し取り組めるような指導をしてあげましょう。
少しでも結果が出たらすぐに褒める! モチベがかなりアップする

どんな小さな成果であれ、それを発見してあげて、思いっきり褒めてあげる。
これも教師に必要なことです。
どんなに反発している生徒でも、「教師に認められたい」という気持ちは、根底にあります。
さらに脳科学的に、「成功体験」を味わうと一種の「快感」を覚えて、再び「その感覚」を得ようとします。
これは、脳の腹側被蓋野という部分が活性化しているためです。
参考学習指導で悩んでいる先生へ!脳科学にそった効果的な教科指導、5つのポイント
褒められることで「認められた」「出来た!」という喜びや快感が得られ、再びその感覚を得ようとして自ら行動し始める。
自ら行動し始めるというのは、モチベーションをあげるため・維持させるためには、必要不可欠ですね。
どんなしょうもないことだとしても、何か全うしたのであれば思いっきり褒めてあげましょう。
「長期目標」を意識させることで、生徒のモチベーションを維持させる

ここまでこればずいぶんとモチベーションはありますから、最後は「それを長く維持させること」に重点を置きます。
長期目標を強く意識することで、「やりぬく力」が生まれ、そのつらさを乗り越えることができます。
長期目標はなんでもいいですが、「お金を得る。」とかよりも、できれば
「自分の存在を喜んでもらうこと」
これを最終目標として、そのための「長期目標」を意識させたいところです。
参考教師もお金の勉強が必要?!7割以上の生徒はお金の授業を聞きたがっている?
幸福感や満足感というのは
他人に、自分の存在を認めてもらうこと、喜んでもらえること
だと思います。
この信用を勝ち取っていくために「具体的に、どのような目標をたてればよいか」が大事になってきます。
理想は
「短期目標」を積み重ねて(並べて)いくと、「長期目標」となっている。
これですね。
難しければ、ゴール(長期目標)を先に決めてから、短期目標を設定していいかもしれません。
長期的な目標(自分が目指したいゴール)を明確に立てさせてやることで、やりぬく意味やその価値などがブレません。
その結果、継続して取り組めます。
モチベーションをアップさせ、継続させるためのコツまとめ
生徒のモチベーションをあげる指導、ポイントまとめるとこの6つ。
- 楽しく学べる環境を作る
- 期待させる
- 成功を前提に会話する
- 短期目標を定める
- 褒める
- 長期目標を定める
このどれが欠けても、バランスが悪くなります。
モチベーションを上げること・維持することが、難しくなります。
モチベーションの源は
- 楽しい
- 目標を達成したい
- 大好きな人に認められたい
の3点と言われています。
この3点を刺激してあげられるような指導をしてあげましょう。
生徒指導に不安があるかたは是非、参考にしてください。