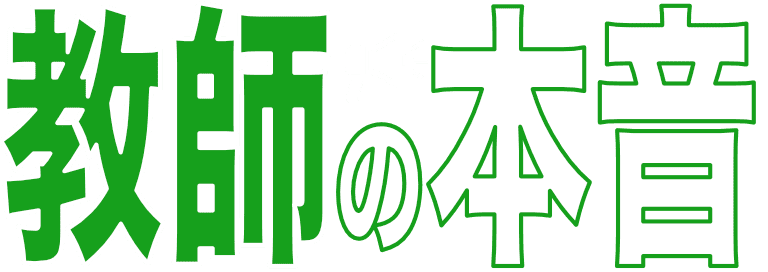あなたがもし
「成果がなかなか上がらない」
「こんなに頑張っているのに報われない」
と悩んでいたとします。
その上で
- 仕事は丁寧だがスピードが遅い
- なかなか定時に帰れない
- 全部の仕事に全力で取り組んでしまう
- 他人に頼るのが苦手
- 先延ばしグセがある
これらに当てはまる人であるならば、この記事と、紹介する本を読んでみてください。
案外、発見できることがあると思います。
あわせて読みたい記事
目次
常に全力で!と考える。「完璧」を求めてしまう教師
教師になる人って、変な人も多いですが(失礼ですね、私の事ですからお気になさらず)
特に小中学校で教師をされているかたは

何に対しても、全力でやらなくては!
と考えている人の割合が多いように感じます。
子どもをもつ親となった今、学校の先生がいい加減な事をしていると(我が子に直接関わる担任や先生なら尚更そう思いますが)、その先生や学校に対して苛立ちや残念感を抱きますし、ちゃんとしてくださいって言いたくなっちゃいます。
さらに、昨今の教師の不祥事。
記事作成時の直近でいうと、2017年8月17日、埼玉県の教師が覚醒剤所持で逮捕された報道がありました。
こういうのがあったりすると余計に、世間からの風当たりというか、イメージが悪くなって
- 少しでも手を抜くとサボっていると言われる
- 高給取り
- いいよな、公務員は無能で努力をしなくてもいいんだから
- 狂師の鑑
と言った心ない中傷をあびる事になります。
口に出されなくても、三者面談なんかで親の意見や口調を聞くと
「そう思ってるんだろうなぁ」
という印象を抱くこともあります。
だからこそ

教師は常に全力でいなきゃ!
って考えちゃいます。
教師はこころから壊れていく人も多い
昨今の教師の立場は、評価される立場です。
- 生徒や保護者から
- 管理職や教育委員会から
評価する眼で周りを押し固められています。
そんな状況のなか、一つのミスすら命取り(離職に追い込まれる)という危機感すら持って教壇に立っている先生もいるのではないでしょうか。
そんな状態が精神的にいいはずもありません。
少し古いデータではありますが、平成24年に文部科学省から出された資料によると、教員の精神疾患による休職者数は増加傾向にあるようです。
参考
資料によれば、精神疾患による休職者数はなんと10年間で約3倍に。
ひょっとすると校種の違いは、教師の絶対数(教師の数)が「高校 > 中学や小学校」となっているので、それに比例しているだけかも知れません。
いずれにせよ、教師は
ココロから壊れていく人が多い
これは事実です。
あわせて読みたい記事
ひょっとすると、努力を認めて欲しいと思っていません?

こんなにも頑張っているのに、周りが認めてくれない

こんなにも努力しているのに、きちんと評価をしてくれない
こんな風に考えたことはありませんか?
もしくは
- 努力をしていない(または、しているようには見えない)同僚を見てイライラする
- 自分より手を抜いているのに、なぜ私よりもいい評価をうけているのだ!
こんな、苛立ちみたいな感情を抱いてませんか?
あなたの周りに居る人たち(生徒、保護者、同僚、管理職、教育委員会等)の目がふしあなで、あなたの評価を正当につけてくれていない可能性はもちろんあります。
しかし。
ひょっとすると、あなたが認めて欲しい内容って、あなたがおこなってきた「努力」を認めて欲しい。
と言っているだけの可能性があります。
努力を認めて「よく頑張ったね」と周りが褒めてくれるのは、小学生までです。
いくら頑張ろうと、努力しようと、結果に結びつかなければ意味はありません。
考えてみてください。
あなたの努力によって得られるものは、あなたに帰属するものばかりです。
生徒の成長や、親の理解が得られるワケでもありません。
あくまでも、あなたの努力によってもたらされた結果がよければ評価されるのです。
参考
世知辛い世の中のように思うかも知れませんが、そんなものです。
努力を認めて欲しい、褒めて欲しいと思うのであれば、身内や恋人、家族、時として自分自身で行ってください。
参考
努力することは当たり前で、結果がすべて
教師、というか教育って「営業成績」は無いですし、売り上げなんか意識しません。
なのでついつい誤解してしまいがちですが、世の中の多くは「結果」がすべてです。
先にも触れたように、うまくいかないと感じてしまっている原因として
- 努力を認めて欲しい
- 努力に美徳を感じている
という可能性があります。
完璧主義の人に多いかな?と思いますが、「努力を認めてほしい」と思っている方には是非
ということを意識するようにしてみてください。
しかも、適度に力を抜きながら効果を上げられるようになればストレスも減るし、効果も上がります。
はじめは手を抜いて「罪悪感」や「後ろめたさ」などがあるかもしれません。
しかし、手を抜きながら効率よく成果を上げる方法を考えて、実践してみてください。
自然と、あなたの努力がダイレクトに成果につながっていきます。
効率よく成果を上げるには

そんな、仕事がうまくいかないと感じている方に読んでもらいたい一冊があります。
参考
という本です。
この本は、簡単に言えば
完璧主義よりも上手に力を抜いて、効率よく成果を上げましょうね
という内容が書かれています。
その中で、ポイントとなるのは
2割に集中して結果を出す
ということです。
完璧主義のいいところもあるが、仕事がうまくいくのは適度に力を抜いている人
力を抜きましょう、手を抜きましょうと言われるとちょっと怖いですか?
- 全部きちんとしないと気が済まない
- 全力で取り組んでいないと、生徒や保護者、管理職や教育委員会から何を言われるかわかったもんじゃ無い
と心配や不安がつきまとうかも知れませんね。
しかし、何度も言うように
- 努力は評価になりません。
- 成果や結果が評価対象になります。
教師も、民間の仕事もこの部分では同じです。
そうであるならば、より効率よく結果や成果を得られる方が、自分にとっても得だというものです。
完璧主義は性格じゃなく思考習慣であるといわれています。
この思考習慣を変えれば効率が良くなります。
さらに、成果を上げられれば何の問題も無くなるし、肉体的精神的ストレスもいくらか軽減されます。
是非努力してもうまくいかないと悩んでいるひとは、成果を上げるために【上手に力を抜く】人になってみましょう。
力を抜いて仕事をする為の極意は
いきなり力を抜いて仕事せい!と言われても出来ませんよね?
なので、ここではまず簡単に、【上手に力を抜く人】の行動をお話しします。
上手に力を抜く人は
何かやるべき事があった場合にチャンクダウンし、小さな一歩から着手する
ということが出来ると言われています。
チャンクとは塊を意味し、チャンクダウンとは塊を細かく分けていくことです。
転じて、やるべき行動を小さく分けていくこと。細切れにすること。細分化などと表現することもあります。
さらに、パレートの法則を意識します。
小さく分けた仕事の内、最重要の部分2割について、最大限の努力をして、残りの8割については覚悟を決めてある程度見放す。
このことをしていく必要があります。
パレートの法則とは?
組織全体の2割程の要人が大部分の利益をもたらしており、そしてその2割の要人が間引かれると、残り8割の中の2割がまた大部分の利益をもたらすようになるというものです。
仕事の成果の8割は、費やした時間全体のうちの2割の時間で生み出しているとも言われています。
要は
ということが大事といえます。
報告書を作る、となった場合
図解 2割に集中して結果を出す習慣術 ハンディ版![]() 58ページ記載内容
58ページ記載内容
報告書を作成する場合、完璧を常に求めてしまう人はいきなりゴールから設定します。

よりよいモノを作らなくては!
って。
そのために
- 使えるデータはどこだ?
- 表現はこれでいいか?
- 抜け落ちているところはないか?
- 文章を打たなくては
- 伝えたいことを追加しなくては
- 誤字脱字を無くして、完璧に仕上げなくては
などと、同時に色々なことを考え、行動に移します。
その結果、長い時間と、ストレスがかかってきます。
参考
話がずれますが、教師をしていてゆっくりと昼休憩をとった記憶はないです。
ご飯も5分や10分で食べる事が当たり前でしたね。
休憩時間って、普通は「30分から45分、長いと60分」もあるんです。
仕事から解放されて「なーんにもしなくていい時間」が毎日あるんですって。
参考
教師の勤務時間問題。長時間勤務は必然?残業で成り立っている現状
ともかく、教師の方は完璧主義の方が多い印象です。
マルチタスク的に、同時に様々なことをしてしまいがちで、その結果非常に効率が悪い。
こんな特徴があります。
先生方の中には、複数の作業を同時にこなせる人もいるでしょう。
しかし、作業を同時にこなせる(スキルがある)からと言って、「同時にしなきゃいけない」ということは絶対にありません。
時間をかけている分
と感じてしまうことも多くなります。
上手に力を抜く人は、報告書を作るときどうするか?
まずは、報告書作成というタスクについてチャンクダウンしていきます。
- データを集めること
- 過去のいい例を探すこと
- たたき台を作る(箇条書きでリストアップ程度)
- 本文を書くこと
- 誤字脱字などを含めてチェックする
ポイントは、分けた項目を同時に行わず、それぞれ一項目ずつ向き合って行っていくことです。
細分化したおかげで、小さな事からすぐにはじめられますし、内容によっては人に任せられたりもします。
民間では部下が居たり事務の人が居たりするので、仕事を任せやすいかも知れません。
教師は、基本横並びなので同僚に仕事を振るということは、実務上難しいかも知れませんね。
それでも
- 担任であれば副担任に(逆もしかり)
- 分掌内や教科内で後輩がいればその後輩に
- 場合によっては、校長や学年主任に。(教頭は、校長と違って雑務に追われて忙しいので(笑))
仕事を手伝ってもらう事は可能かと思います。
先の例で言えば
- データを集めること
- 過去のいい例を探すこと
- たたき台を作る(箇条書きでリストアップ程度)
- 本文を書くこと
- 誤字脱字などを含めてチェックする
これらのうち
本文を書くこと(と、たたき台をつくること)は、自分で行うべき重要事項です。
それ以外のことは、誰でも出来ます。
他の誰かに任すことが出来ないのであれば、隙間時間(通勤や移動時間など)を利用する事だって出来る内容ですので、そうやって効率を重視してください。
日々の授業も同じで、手を抜いて2割を意識する
授業の展開(教える内容)だってそうです。
50分なら50分間、まるまる知識を教え込もうとしていませんか?
伝えたい内容、話さなくてはいけない内容を2割にまで絞ってください。
その他は力を抜いて、演習や世間話などを組み込んでもいいですね。
今流行のアクティブラーニングの観点から、生徒自身が主体となって取り組める内容を組み込んでもおもしろいかも知れません。
参考
アクティブラーニングを高校の授業でしたいけど、グループワーク以外に思いつかないあなたへ、3つのポイント
アクティブラーニングという言葉が流行し始めて2年~3年ほどが経ちます。教育の現場にいれば割と耳にすることが多くなったこの「アクティブラーニング」という言葉ですが、実際のところよくわかっていない、という方は多いのかなと思います。[…]
最後に
生徒は賢いです。(成績とか頭の回転とかもひっくるめて)
こちらがいちいち指示しなくても、割と要領よくやろうと勝手にします。(大概の場合は、効率を考えて手を抜くというよりは、サボりたいから手を抜く方が多いと思いますが・・・)
こちらが、手となり足となり動かなくても、頭として動いて上げれば、自然と動き出します。
なんでもかんでも完璧にこなさなくては!と言う考えは捨てた方が、自分のためにもなります。
教師の努力は報われません。
生徒が何か成功を収めれば、それは生徒の評価になるし、生徒が何か失敗すれば教師に責任が及びます。
それが現在における、教師の立場です。
生徒のために、そして何より自分のためにも
上手に手を抜いて、力を抜いて。
あなたの努力が「より効果的に、高い成果をうみだす」ために必要な思考・行動習慣を身につける。
これを意識してみては?
こちらもおすすめです。
ちなみにシンプルに結果を出す人の 5W1H思考![]() は、
は、
課題提起、問題発見・問題解決、創造的アイデア発想、説得力のあるコミュニケーションなど、日々の業務のさまざまな場面で、あなたのパフォーマンスを高めてくれる
内容です。
仕事の生産性を高めたいと考えている、すべての方におすすめですし、以下の項目に当てはまるような人にはオススメの1冊です。
- 思考・発想法を学んだが、うまく活用できていないと感じている
- 物事の細部に入り込みすぎてしまい、「視野が狭い」「もっと全体を見て考えろ」「目的を忘れるな」とよく指摘される
- 本質的な問題設定や抜本的な問題解決が苦手である
- 説得力のある戦略プランが提案できない
- アイデアを出しても、「数が少ない」「平凡だ」とよく言われる