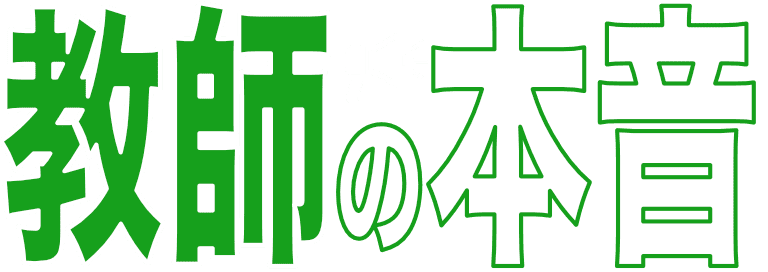教師の大事な仕事、それはもちろん毎回の授業です。
部活指導でも、分掌業務でもありません。
授業です。
それ故、悩みも多く、色々と試行錯誤もされたり、場合によっては諦めも出てくるかもしれません。
そこで今回は、授業の展開で役立つテクニックを4つお伝えします。
目次
1回の授業で伝えたいポイントは1つか2つに絞る
(ブログをやっていると徐々にわかりますが)1記事にいくつもテーマがあると、ポイントがズレて、結局何が言いたいのかよく分からなくなってしまいます。
授業も同じことが言えます。
伝えたいポイントは絞りましょう。
人間の集中力なんか、たかが15分から30分しか持ちません。
そんな短い時間の間に、3つも4つも大事な事は覚える事は出来ません。
人の集中力は30分、伝えるべき内容のテーマは2つが限界。
個人差はあるでしょうが、1回の授業で2つのテーマが限界です。
カリキュラム、年間指導計画、テスト範囲など、授業の進み具合にもしがらみもあるでしょう。
しかし、それらがありきで授業をしてしまっては本末転倒です。
なんのために授業をしているのか分からなくなりますし、聞いてる方も知識欲を満たすのではなく、詰め込む作業をしているだけになります。
詰め込む作業だけでも
- 受験に役立つ
- テストで良い点が取れる
という点のみメリットはあるかもしれませんが、そんなものが社会に出て活かされる機会はまずありません。
授業のコンセプトとしては
といったスタンスで授業を行うよう心がけてください。
繰り返しになりますが、人間の集中力などせいぜい30分。
テーマがあちらこちらに散ると、効果的に記憶していくこともままなりません。
それをカバーするための板書であり、定期テストとも言えるでしょう。
動物界で唯一、人間は知識を得ることで欲を満たすことができます。
雑学にしろ小ネタにしろ

といって、独特の満足感を得られるのは人間だけです。
授業も知識欲を満たしてあげることに念頭に置いてみてください。
驚くほどスムーズに授業展開が出来ますし、聞いている生徒たちもポイントが明確になって聴きやすくなります。
授業のポイントを1つや2つ絞るテクニックとしては、まずメインテーマ(柱)を決めましょう。
そこに、必要な付加情報(知識)を肉付けしていき、50分なら50分の授業を組み立てるという方法です。
そうすると、自分自身も話しが整理しやすくなりますし、展開に強弱もつくので授業にメリハリが付きます。
ぜひ試してみてください。
黒板は授業が終わった後で見返すと、内容が一目瞭然となっている、が理想
黒板の幅には限界があり、書いては消してを繰り返し返すことも多いと思います。
黒板の大きさにもよりますが、50分という授業であれば、往復2回が限界だと私は思います。
それ以上では、授業は単に写経の域に達し、教師の存在は必要ありません。
個人的には
で収まるようにしていました。
教科書ではありません。
教師は、その職業柄ついつい

と足し算をしたがります。
引き算が苦手です。
ファッションと一緒で、足し算ばかりではごちゃごちゃしてまとまりがないばかりか、結果として残るのは

という満足感だけです。
教えてる教科内容の魅力も知識も、一切伝わりません。
なかなか生徒が理解してくれないと悩んでいる方は、板書のレイアウトを考え直しましょう。
使う色は3色以内(色覚にも注意)
板書に関係する事柄がもう一つ。
基本黒板であれば白チョークがメインだと思いますので、そのほかにあと2色ということになります。
記事なんかもそうですが、ごちゃごちゃカラフルに描かれた文字やイラストは見ていて疲れます。
生徒は賢いので、そういったゴテゴテ感が好きな子は自分で勝手に装飾しています。
光の三原色や色の三原色といったように、基本人間は3色をベースにものを見ます。
その3色の組み合わせで様々な光が色を認識するわけですが、4色以上だと
- 色調の判断
- 色の強弱の判断
に重きが置かれるようになっていき、授業のポイントが散ります。
無難は「白、赤、黄」の3色だと思いますが、出来れば蛍光色のチョーク(オレンジがオススメ)を使うと良いでしょう。
生徒の中には、色覚異常の生徒もいると思います。
本人がそれほど自覚していなくても、実は見えていなかったという事態もあります。
そういった意味でも、緑の上に赤という文字は避けたほうが無難といえます。
私は、黒板自体で緑という一色を使っていると判断して、基本2色で授業を行なっていました。
先ほど黒板はポスターだとも言いましたので、その観点からいうと目立つ配色が大事では?と誤解する人もいるかもしれません。
しかし、黒板はメモ帳よ代わりとも言っていますので、その点だけは誤解なきようお願いしたいところです。
教科書を覚えるではなく、教科書で覚える
これは特に理系の科目で大事になってきます。
難しい言葉を難しく説明するのは誰でも出来ます。
授業で大事なのは、難しい言葉を
- いかにわかりやすく
- いかにイメージしやすく
- いかにすんなりと
理解してもらうかがポイントになります。
教科書を教えていては、絶対に理解してもらえません。
教科書を使って、理解してもらうのです。
違い、わかりますか?
教科書は、単に小道具のひとつということです。
参考
今や国民の1人に1台が持っていると言われいているスマートフォン。スマートフォンが普及して(アプリでできることが増えて)、便利なことや気軽に試せることが増えました。 タブレット端末と併せて、教育現場でも利用される[…]
やりかたはいくらでもあります。
- 教科書に書いてあることをそのまま黒板に書く
- 教科書に書いてあることをそのまま話す
こういったことが無いように、授業を進めてください。
私は物理を教えていたので、よくアニメの世界と現実世界のギャップについて、物理学の観点から迫っていました。
参考
物理教師アニメのサイト
反省としては
- 脱線しすぎて授業が進まなかったり
- 物理の本質より、その内容そのものに興味が移り、肝心の物理内容についてはおろそかになってしまったり
してしまうこともありましたが。
無駄な話ができるような、心と時間の余裕をもつこと
これが一番大事かもしれません。
教科指導というと、一番は専門知識があるかどうかです。
その分野についてそれなりの知識をもっており、問題解決へのプロセスが見いだせる。
そんな力量は、当然求められます。
しかし、問題解決ばかりを前面に押し出された授業って、振り返ってみてもあまり思い出せないんですよね。
もちろん、生徒は問題も解けるようになるし、知識を生かすこともできてくる。
でも記憶に残っている授業内容って
- その先生の身の上話
- ちょっと面白い小ネタ
だったりするんですよね。
要は、どうでもいい話や無駄話。
その教科が好きだから、先生が好きとなる生徒はそういません。
しかし、先生(あなた)が好きだからその教科が好きとなることは、大いにあります。
そして、生徒を引き付ける人間的魅力は、雑談力にあると思うのです。


と思わせれば、多くの生徒はあなたを魅力に感じて、教師として好きになってくれます。
生徒が何気なく発した一言を拾えるくらいの、心と時間の余裕を持ってください。
その一言を広げられるくらいの、豊富な教養も身に着ける努力をしてください。
一見、教科指導に役立たなそうな内容でも、生徒を引き付けることができれば、信頼関係が構築され、まわりまわって教科指導がしやすくなります。
まとめ
即授業に活かせないものもあると思いますが、授業に役立つ4つのポイントを整理しておきます。
- 1回の授業で話すポイントは、2つまでに絞る。
- 黒板は、授業が終わった時に何を教えていたか、ぱっと見でわかるようにする。
- 教科書を覚えるのではなく、教科書を使って覚える。
- 無駄話ができる、心と時間の余裕をもつこと。
この4つを意識して、授業をしてみてください。
初心者の頃って、ついつい余裕がなくなってテンパってしまいますが、誰しもが通る道でもあります。
あなただけができていないわけじゃないので、そこは安心してくださいね。
あわせて読みたい記事