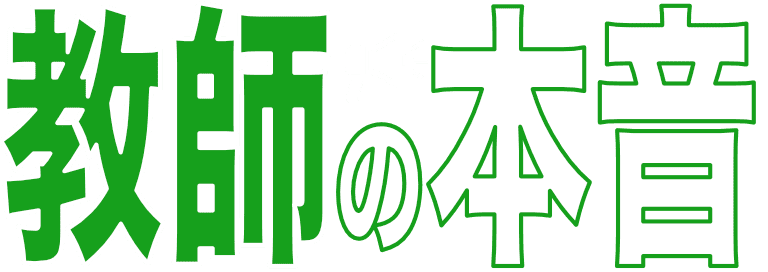年度当初は特に、個人面談や家庭訪問など「保護者・生徒」と話す機会が増えたり、はたまた「初任者や新たなパートナー」と話す機会が増えると思います。
そんなとき、気を付けたいのが
相手を「ヤル気にする」声かけになってる?
ということ。
本日は
- ちょっとした意識で変えられる
- 聞き手にとって効果的
そんな「表現・言い回し」を意識しませんか?という提案です。
(年度当初に)面談をするうえで気を付けたい内容について触れながら、話を進めていこうと思います。
目次
正しい言葉を選んで、受け取る印象を変える

どうやら褒められている。だけど

どうも褒められている気がしない。…皮肉?
こんな経験はありますか?
口調や表情、語気など「言葉以外」にある微妙な変化によって、人は多くの情報を「補完」して受け取ります。
そんな「言葉以外」が受け手の印象に影響していることは多いです。
しかし、そもそも発せられた「言葉」自体に問題があり、話し手が意図していない伝わり方になっていることもあります。
特に、「○○してみたら?」というような提案をする場合。
あなたが選んだ「言葉」が、受け手にとって「縛りがきつい・選択肢を狭めている・良いイメージが持てない」なんてことになっている可能性は考えたほうがいいかもしれません。
2割貯金しろ!と、8割で生活してみなさい
10年以上も前の(確か証券会社かなにかの)CMだったと思いますが、いまだに頭に残っている表現があります。
給料の2割を貯金しなさい、というと若者は「できません」という。
給料の8割で生活してみなさい、というと若者は「やってみます」という。
リーダーシップとは?生徒に響く「声かけ」の違いについてでも話していますが、教師は生徒の成長段階に応じて
目的達成の手段(方法)を、伝えるような声かけ
をおこなう機会も多いハズです。
要は、あなたから生徒へ「提案する」こと。
特に面談では「命令する」ということよりも、「提案する」ことの方が多くなるんじゃないでしょうか?
そんなとき、提案した内容が「制限の強い内容」だと、受け手にとっては「本質(目的)を見失ってしまう」かもしれません。
さっき紹介したフレーズ。
給料の2割を貯金しなさい、というと若者は「できません」という。
給料の8割で生活してみなさい、というと若者は「やってみます」という。
これ、どちらも「貯金」してみては?という提案です。
まぁ、実際問題として
貯金に不慣れな人ほど「(半)強制的に」行わないと、たまっていかない
という事実はありますが、とりあえずそこは置いときます。
大事なのは
提案された内容が、受け手にとって「自由度の高い内容」じゃないと「提案」にならない可能性がある
ということです。
2割に注目させても、残り8割に注目させても結果は同じです。
しかし印象は随分と変わってきますよね?
同じ内容を伝えているのに、いまいち伝わらない場合は「別の視点」「残りの部分に注目」という意識が大事になってきます。
ミスリードやノイズで、伝えたい内容ネガティブに伝わる?

例え話を続けます。
次のようなことを聞かされた時、あなたはこの「食べ物」を食べたいと思いますか?
- 多くの日本人が、好んで食べている食べ物です。
- タマゴ、チーズ、バター、ワイン、オリーブオイルなどと相性抜群な食べ物です。
- 乳ガン患者の8割近いひとが、朝食時にこの食べ物を食べていました。
- 欧米では、死ぬ直前に口にする人が多い食べ物です。
これを聞かされたあと
とすすめられたとき、素直に

はい、喜んで!
とは言いにくいんじゃないでしょうか。
ちなみに答えは「パン」(のつもりで設定しました)
おそらく引っかかるポイントは、後半の2つ。
- 乳ガン患者の8割近いひとが、朝食時にこの食べ物を食べていました。
- 欧米では、死ぬ直前に口にする人が多い食べ物です。
「(強烈なインパクトである)死」を連想させるフレーズにより、素直に「食べたいです」とはならなかったと思います。
もしこれが「あなたにパンを食べてほしい」と思った上で伝えた内容であれば、良い言葉選びとはなりませんよね。
言葉や表現を置き換えてみよう
先の情報は、どれも事実かもしれません。
しかし
提示する順番を入れ替えたり
表現を変えたり
という工夫一つで、「食べたい・食べてみたい」と言いやすくなります。
順番を入れ替えるだけでも、印象が違う

生徒や保護者との関係をうまく築きたい方必見!誰も教えてくれない7つのテクニックで話していますが、たくさんの情報が入ってくると
最後の情報に左右される
ことが多いです。
これを、親近効果といいます。
詳しくはこちら参考生徒や保護者との関係をうまく築きたい方必見!誰も教えてくれない7つのテクニック
例えば、これを利用して「最後の情報」に気を付けてあげれば
- 欧米では、死ぬ直前に口にする人が多い食べ物です。
- 乳ガン患者の8割近いひとが、朝食時にこの食べ物を食べていました。
- タマゴ、チーズ、バター、ワイン、オリーブオイルなどと相性抜群な食べ物です。
- 多くの日本人が、好んで食べている食べ物です。
少し印象が変わりませんか?
特に日本人は「みんなやってる」「みんな好き」など、周りが始めたことや、すでにやっていることに対して

隣がやっているなら、私も…
と思うのが得意な人種です。
個人的には、徐々に効果が薄れてきているかなと思いますが、「みんなそうだよ。」という提案は、学生を相手に提案をするならまだまだ有効だと思います。
ただし、多用は禁物です。周りと比べてばかりじゃ成長がありませんから。
親近効果を意識して、伝える順番を入れ替えてあげる。
これだけでも、伝わり方が随分と変わってきます。
言葉を置き換えてあげる

脳内で考える時間があるなら(思いつきでしゃべっていないなら)、表現を変えてあげることも意識してみましょう。
さっきの入れ替えた表現
- 欧米では、死ぬ直前に口にする人が多い食べ物です。
- 乳ガン患者の8割近いひとが、朝食時にこの食べ物を食べていました。
- タマゴ、チーズ、バター、ワイン、オリーブオイルなどと相性抜群な食べ物です。
- 多くの日本人が、好んで食べている食べ物です。
これとほぼ同じことを言いながら、言葉を置き換えてあげます。
- 欧米では、死ぬ間際でも食べたいと思う人が多い食べ物です。
- 朝食時、これを食べずに乳ガンになったひとは、患者全体の2割にのぼります。
- タマゴ、チーズ、バター、ワイン、オリーブオイルなどと相性抜群な食べ物です。
- 多くの日本人が、好んで食べている食べ物です。
いかがでしょう。さらに印象が変わりませんか?
同じことを伝えているハズなのに、表現ひとつで全然印象が変わってきます。
面談などで提案の話をするとき、気を付けたいこと
あなたは良かれと思って相談に乗ってあげる。チカラになってあげる。
そのとき、せっかくの提案内容や褒めた内容がきちんと伝わらなければ、残念ですよね。
しかし、言葉選び一つでも結構変わってくるものです。

言っていることが、いまいち伝わってないのかな?
と感じたら、面談時などにおいて相手(生徒)と話す場合、以下の内容に気を付けてみてください。
制約の強い提案は、命令と同じ
参考「強制的に2割」より「柔軟な8割」の方が、受け手は受け入れやすい。
親近効果を意識して、話す順番を入れ替える
参考たくさん情報を伝えた場合は、最後の情報がよく残る
日本人は、「みんなやっている」に弱い
参考「諸刃」的危険性があるので、使い方には気を付けたほうがいいですが、有効な表現の一つ。
別の視点・残り部分に注目させるなど、表現の工夫をする
参考同じ「事実」でも、フォーカス(焦点)次第で印象が変わります。
伝え方や表現は、「こうあるべきだ!」というような決まったものがありません。
むしろと画一的に決めてたら、人間味が無くて「ロボット」がやっていることと同じです。
そうなると人間の先生は不要ですね。
当然、「熱量」をもって生徒や職場の同僚と接することが大事ですが、うまく伝わらないことが恒久的である場合は、ぜひ表現を変えることを意識してみましょう。
提案の次ステップである「命令」の場合は、こちらの記事が参考になります。