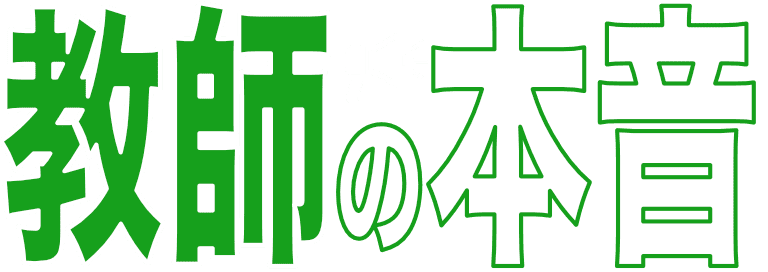アクティブラーニング、学習指導要領改編、学級経営、部活動指導、大学入試改革などなど、現場ではあまり深く教えてくれないことは、自身でアンテナを張って、情報を得ていく以外に手はありません。
学校や教育委員会が用意している研修会なんて、あって無いようなものですからね。
そこで本日は、高校教師のあなたにぜひ読んでほしい7冊について紹介します。
目次
アクティブ・ラーニングについて詳しく書かれた本
最近では「アクティブラーニング」という言葉が先行して広まってしまったため、それを教えなさいと言われている現場が混乱しているように思います。
同時期に広く広まった
とごっちゃになっている人もいるかもしれませんね。
アクティブラーニングとは、平たく言うと
のことだと言われています。
アクティブラーニングについては、以下の記事も合わせてどうぞ
アクティブラーニングを高校の授業でしたいけど、グループワーク以外に思いつかないあなたへ、3つのポイント
そこで今更聞けない<b>アクティブラーニングについて、3冊おススメの本を紹介します。
高校教師のためのアクディブ・ラーニング
それに伴い、授業は(生徒は・先生は)どう変わるのか? ということにスポットを絞り、高校の先生方にとって大変実用的な内容になっています。
単純に理論を展開するだけでなく、実践例も掲載してあるので即実践しやすいのも特徴です。
部活に例えた説明や、アーリーマジョリティの考え方が大変説得力がありました。
アクティブ・ラーニングを促す一手法として非常に参考になります。
これからの高校教師に求められる指導方法がまとめられている良本です。
アクティブラーニング入門
小林先生は、私と同じ物理の先生です。
この本のポイントは長年の現場経験に基づいた実践的かつ理論的な内容になっているところです。
アクティブラーニングとは何かから始まり、その意義や背景に加えて、経験に基づき、どのように高校物理の授業でアクティブラーニングを実際に行っていたのかを知ることができます。
本書の大変素晴らしいところは、アクティブラーニングの理念だけでなく
が多くあるところです。
例えば、時間配分。
著者の勤務校は65分授業だったようですが、その65分の内「説明15分、問題演習35分、振り返り15分」に分けて実践していたこと。
また、問題演習では難易度のことなる問題を4~5題を出し、クラス全員がテストで満点が取れるように「聴き合い・学び合い」を大事にしてたこと。
生徒に安心安全な教室空間を作ることを重視し「注意ではなく、疑問形式で行動の振り返りを促した」こと。
などなど、アクティブラーニングの具体的な手法がわかりやすく書かれています。
アクティブラーニング入門2
主体的・対話的で、いわゆる「深い学び」の実現をしたい!と考えている先生の参考になること間違いなしです。
特に、授業改善に活かせそうな内容やテクニックに重点を置いた本書の解説は、アクティブラーニングをこれから授業に実践しようと考えている人にも、実践してはいるもののうまくいっていない方にも、いずれにしても役立つ内容になっているといえます。
また、本書にはDVDが付属しており
- 初対面の高校生に向けての小林の授業の実際
- 小林の授業の概略
など、<b>よりわかりやすくアクティブラーニングを導入するためのテクニックが学べ、アクティブラーニングの解説書として活用できること間違いなしです。
センター試験が変わる?!教師に求められる内容も変わる?
アクティブラーニングのあおりもありますが、ご存じのとおり、2020年から大学入試の試験方法が大きく変わります。
時代のうねりもあって教育困難大学なんて言葉も流行っているようです。
より主体的に学んだ成果を(能力を)判断するために、たとえば英語ではスピーチや書き取りに重きが置かれたり、いわゆるマークシートによる選択式の回答方法じゃなくなると言われています。
研修会等で学ぶ機会もあるとは思いますが、そのあたりについて不安な方のために、1冊ご紹介しておきます。
2020年からの教師問題
これからは「大学入学希望者学力評価テスト(仮称)」と呼ばれる新たな試験が実施されることとなります。
このことは多くの方が知っているでしょうが、このセンター試験廃止の背景には、文科省による大規模な教育改革が存在していたことまできちんと知っていますか?
学校教育は「知識の習得」を中心とした従来の学習から「知識の活用」を目指すスタイルへと大転換を迫られているといっても過言ではない現在。
今の高校現場に求められるであろう、教育活動のいわば改革を、実践・実行していくためには何が必要なのかについて書かれているのが本書になります。
先に紹介したアクティブラーニングとさらには高大連携の動きについてもわかりやすく解説してあり、現場の教師(特に高校現場)に向けて、すぐに活かせる内容になっています。
大学入試の内容はもとより、これから生徒が求められることになる「知識の習得」から「知識の活用」に対して、教師としては何を生徒に伝えるべきなのか。
なぜ知識の習得だけではダメなのか、知識・理解なくして自分の意見は述べられるのか、教養教育の見直し、グローバル・スタンダードとしての世界に通用する本当の教養とは何か、ゆとり教育の成果はあったのか(どちらかというと本書は肯定派です)、などなど本書は「求められる学力について」いろいろ考えさせてくれます。
指導方法や具体的な実務について情報を得られる本
アクティブラーニングや、学習指導要領の改編、大学入試の変更などトレンドに即した内容よりも、学級経営や、生徒指導、教科指導について、見聞を広めたいと思うこともあるでしょう。
そんな方に向けておススメな3冊をご紹介します。
高校教師のための学級経営365日のパーフェクトガイド できる教師になる! 3年間の超仕事術
具体的で役立つ実物資料や、感動のホームルーム、卒業式の実話をもとにした話も載っており、興味深く読み進めることができます。
いわゆるマニュアル本ってやつですね。
これを読んでそのまま実践に移すというよりは、一つのネタ帳というか参考書のような扱いで利用していくのがいいかな、と思います。
学ぶ心に火をともす8つの教え 東大合格者数公立No.1!! 日比谷高校メソッド
本書に書かれている「8つの教え」を実践している日比谷高校は現役東大合格者数を急激に伸ばしました。
東大に入ることが絶対的に正しいとは言いませんが、少なくとも知識欲に長けた生徒が多いのは疑うことはありませんし、その後の日本を背負っていく人材になっていく、ということに間違いありません。
「勉強しなさい。」と言えば言うほど、子どもは勉強を嫌がるものですよね。私もよく反発していました。しかし、立場が変わればついつい言ってしまう。
本書を読むと、「勉強しなさい。」なんて言わないでも、子どもを勉強に向かわせることできるかも?と思えるようになってくるから不思議です。
大学受験に的を絞った私立中高一貫校と競うのではなく、公立ならではの、3年間、勉強だけでなく文化祭や課外活動にも全力で取り組む基本姿勢が重要だということが述べられています。
勉強もそれ以外の行事や課外活動も、人間力を高めるためには両方必要であり、それによって学力も伸びること、それの延長線上に「東大入学」があり、ひいては日本を背負っていく大事な柱となっていってほしいという思いが読み取れます。
さらに学校でいちばん大事なのは授業であり、その授業は「楽しい授業」であるべきだということも書かれています。
「なぜ」を問う授業によって知的好奇心を刺激し、学ぶ心に火をともすことができ、ひいては知識を蓄積する学習にも主体的に取り組むようになる、ということが書かれています。
高校教師入門―仕事の進め方・考え方
そのいずれも、「いわゆる抽象的な内容で、あとは自分で考えてやってね!」みたいな無責任な内容になっていなくて、具体的な手法や、犯しがちな過ちが挙げられていたり、単なるアイディアになることなく、著者が実際に考え行ってきた教育活動、その経験に基づく内容が書かれているため、非常に説得力を持った内容となっています。
教師になったばかりの方に向けてももちろんですが、複雑化してきた現在の高校現場で、悩みを抱えている先生なんかにはぜひ読んでほしい一冊です。
教師だけど話すのが苦手なあなたに、おススメしたい簡単な4つのテクニック