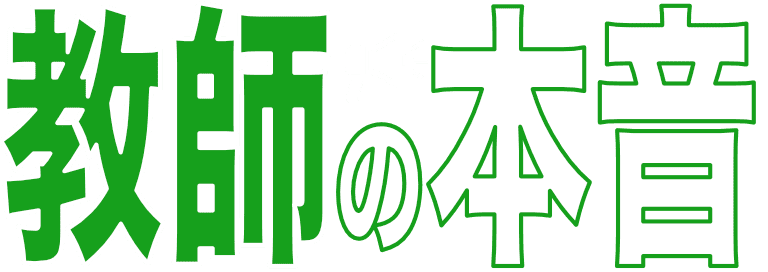2018年10月2日、第4次安倍内閣が発足しましたね。
くらいの印象しかありません(失礼)。
しかし発足直後、なかなかショッキングな会見がありました。
(教育勅語を)アレンジをした形で、今の例えば道徳等に使うことができる分野は、私は十分にあるという意味では、普遍性を持っている部分が見て取れる。
同胞を大事にするなどの基本的な内容について現代的にアレンジして教えていこうという動きがあり、検討に値する
引用 初入閣の柴山文科相、教育勅語“普遍性持つ部分ある” -TBS NEWS
初入閣を果たした柴山昌彦文部科学大臣は、自身の就任会見で「教育勅語」を引き合いにだして発言し、その発言が話題となっています。

何で教育勅語に触れると、問題になるんだろう?
本日はそんなあなたのために
そもそもなぜ、教育勅語がアカンのか?
こんなところについて、記事を書いていきます。
目次
教育勅語とは?
教育勅語。
学校の歴史の時間で習った覚えがある私ですが、すらすらと説明できるほど詳しく覚えていませんのネットの力を借りることにします。
ウィキブックスによると
教育勅語(きょういく ちょくご)とは、正式には「教育ニ関スル勅語」といい、1890年(明治23年)に発表された、第2次世界大戦前の日本の道徳教育の根幹となった勅語(ちょくご)である。
教育勅語の中身は、大まかに言うと、道徳教育の主張である。いわゆる「親孝行」などの「道徳」を尊重するような意見を、天皇が国民に語りかけるという形式である。
「勅語」(ちょくご)とは、一般的な用法での意味は、天皇が政治・行政などについての意思表示として伝える、天皇のいわゆる「お言葉」を、文書などとして正式化し公表した物である。
なお、第二次大戦後、教育勅語は廃止された。
引用 ウィキブックス
このように記載しています。
教育勅語の何が問題なのか?
私が思う、教育勅語を引き合いに出して問題視される要素は、以下の通りです。
- 思想や良心の自由を押しつける。
- 戦前当時の歴史的・政治的な背景から生み出された言葉である。
- 普遍的な道徳について語るのに、わざわざ教育勅語を持ち出してくる必要性が感じられない(裏があるとしか思えない)
もう少し踏み込めば

(有事の際は)お国のために、命を捧げよ!
と言われていた時代に教えられた道徳を、アレンジしようが何しようが、土台としてそんなものを引き合いに出してくること自体がナンセンスなんだよ。ってことですね。
参考
進撃の巨人空想科学読本についてレビュー

でもさ「夫婦や親兄弟など ”愛すべき人たち” を大事にしましょう」って、大切なことだと思うし、それって別に問題じゃないのでは?
と思う人も多いと思います。
だからこそ、パンチやインパクトがほしかったからなのか、ほかの思惑があったからなのか分かりませんが
それ(いわゆる道徳的な内容)だけを全面に出せばよいのに、「教育勅語に書いてあるように」とわざわざ前置きをしたことが問題
だと考えます。
ほかにもあった! 教育勅語が絡む問題
今回の文科省の新大臣の発言以外にも、教育勅語を引き合いに出して問題になった例があります。
防衛大臣の発言
2017年3月、当時の防衛大臣であった稲田さん(眼鏡をかけた女性)も、教育勅語を引き合いに出しています。
教育勅語がいっているところの、日本が道義国家を目指すべきという、その精神をそれは目指すべきだという考えは変わっていないと
引用 ”教育勅語”精神は取り戻すべきー日テレNEWS24(2017年3月9日)
国有地格安売却問題でスポットを浴びた森友学園
引き合いにだして問題になった訳ではありませんが、国有地を不正に値引し売却させたとして問題になった森友学園。
この森友学園が運営する「塚本幼稚園」で教育勅語教育なるものが指導されており、教育勅語の暗唱などが行われてきたというものです。
森友学園は、同市淀川区で運営している塚本幼稚園で毎朝、教育勅語を暗唱させていることで知られます。
引用 「教育勅語」教育は不適切ーしんぶん赤旗(2017年2月24日)
教育勅語に絡む問題について、まとめ
教育勅語については、1948年(昭和23年)に衆参両院で「排除」「失効確認」がなされているようです。
1948年6月19日に教育勅語について、衆議院では排除、参議院では失効確認がされた。
引用 ウィキブックス
今回の大臣の発言で、現在でもなお

(歴史的・政治的な背景は無視して)書かれている内容については、良いことが書いてある。
と考える人が多いことがわかりました。
もちろん、家族や友人、パートナーを大事にするといったものや、すすんで良い行いをしましょうといった道徳は大事ですが、教育勅語に書かれていたから大事なのでは無いと思います。
道徳心を育てる、思いやりの心や愛情をはぐくみたくなるような教育をしていきます! って内容なら良かったのになぁ。
いずれにせよ、国の教育を担うべきトップからでた発言としては、残念(むしろちょっと怖い)と思えて仕方が無い会見でした。
教育勅語には良いことも書いてある・・・じゃなくて、そもそも良いことはどこにでも書いてある。それこそ普遍に。
これに気がついてほしかったですね。