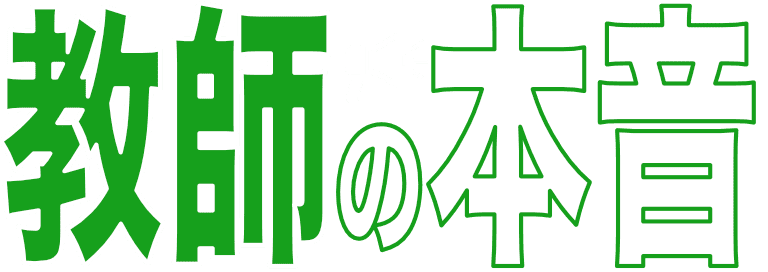突然ですが、ここで問題です。
○○教育
空欄(○○)に入る適当な言葉を答えなさい。
実は、正解数が80~140個くらいもあるらしいので、大概思いついた答えは正解だと思います。
そしてこれの何がすごい(怖い)って、そのほとんど全てを
今の教師は教えるべきである
って(暗に)言われて、授業やカリキュラム、先生自身の研修として組み込まれている事なんですよね・・・。
本日はそんなお話です。
目次
日本の先生は教えることが多すぎる?

冒頭の問題の答えですが、一例を挙げると以下の通りになります。
- 国語教育
- 算数教育
- 英語教育
- 道徳教育
- 国際(理解)教育
- 交通安全教育
- 防災教育
- 金融教育
- 情報教育
- プログラミング教育
- キャリア教育
etc・・・
探せばたくさんあるようです。
「○○指導」って言葉もそうですよね。
- 部活指導
- 生徒指導
- 進路指導
- 教科指導
etc・・・
日本では小学校の先生なら1人で30人~40人の児童(生徒)を見ます。
中学や高校なら担任・専任制になるので、100人~250人くらいの生徒を見ます。
それぞれの子ども達に対して私たち教師は、上記に挙げた「○○教育」を意識しながら「教科指導」を中心に授業や教育活動をすすめていくように・・・って言われていますよね。
・・・。
全部一人で教えてたら、ワンオペブラック企業も甚だしいですよ。
と突っ込まずにはいられません。
ホント、日本の先生は教える(べきとされている)ことが、多すぎる印象です。
多くのことを教えるため、校則があるはずなのに

ホント今の先生に求められる力って、ものすごく多岐にわたっていますよね。個人の力じゃとてもカバーしきれないので、同僚とチームを組んで・・・とか「学校全体として」取り組んでく、って事が大事になってくるんでしょう。
そんな中でもわかりやすいのが校則。
本来「校則」って、多岐にわたる教育活動を円滑に進めるためにあるはずです。
でも現役や既卒生たちなど「生徒たち」にとっては

学校で学んだことなんて何にも役に立たなかった。

校則超うざい
って感じで、伝わり方もさまざま、残り方もさまざま。
教育したことはほとんど残らず、校則に至っては「ペナルティ」「罰則」だけが残って、本来の目的が薄れちゃってますよね。
参考:【ブラック校則撤廃について】高校教師・現場経験者だからこそ感じること
先生個人はもちろん、学校としても限界を感じる
学校教育にも
創意工夫が大事
PDCA(計画・実行・評価・改善)が大事
と言われるんですが、なんせ○○教育って100種類前後あるんですよ・・・。
一つのイベントや企画に対して、創意工夫やPDCAを回すなら、時間的・肉体的・資産(予算)的にもじっくり時間をかけてあげることが可能でしょうが、なんせそれを「100通り」考えなくてはいけませんからね。
参考
自分(学校)がよかれと思ってやっている教育的指導も、人によっては全く響いておらず。
何もしなけりゃ何もしないで無能扱い、税金泥棒扱い。
小学校の時に交通安全教育をしていても、中学生になればスマホ見ながら歩き始めるし、大人になれば信号無視だってする。
成長は鈍化することである。
と、昔教育関係の講義で聞いた事がありますが、鈍化を通り越して劣化だと思っちゃうんですよね。
先生個人や学校として、いい加減成長するためにも
これをしないと、限界がきてしまいます。
今後の日本の教育はどうなるのか?

以前「これからの教師の仕事はどう変わる?!」でも今後の先生の存在意義みたいなのは話しましたが、今後の日本が取るべき教育の方向性、ひいては
ってどうなっていくんでしょうね。
例えば学校の在り方については、大きく2つに分けることができるようで
画一的・平等・無償の方向性、公的責任
日本はどちらに進みたいんでしょうか。
それぞれ有名なところ(教育の実績をあげている国)で言えば以下があげられます。
学力重視で出生や身分に関わらず、結果のみ(テスト)で判断するという意味で平等を実現し、「格差化」を重視したシンガポール。
教育や学校は社会的な意義が高いと考え、完全無償化を実現、民族的な背景もありながらも「協調的」を重視したフィンランド。
日本のお偉いさんや(一部の?)教育評論家達は「フィンランド」の方に舵を切ろうとしている雰囲気がありますが。
今後の日本の教育、日本の学校の在り方ってどうなるのでしょうか。
私としては、冒頭説明した通り〇〇教育と名のつくものが100種類以上もあるような教育スタイルがそもそもアカンと思うので、まずは
これが大事なんじゃないかなぁと思います。
なんでもかんでも「詰め込もう」「新しいものを取り入れよう」とする従来のやり方を根本的に見直す必要があると感じます。
主体的対話的深い学びを!と叫んで「アクティブラーニング」を導入するのは結構ですが、部活動を切り離したり、教師のやるべきことを明確化することが、超重要だと感じます。
先生に求められている力とは


という前に、今の先生に求められている力とは
これが必要だと感じます。その上で
- 熱量を持って指導する。
参考生徒のモチベーションをあげる指導、ポイントはこの6つ! - 先生自身のスキルを向上させる。
参考教師にオススメの資格 - コミュニケーション能力を高める
参考初めに声をかけてくる教師は、力になってくれるのか?同僚との付き合い
こういったのが大事になってくるんじゃないでしょうかね。